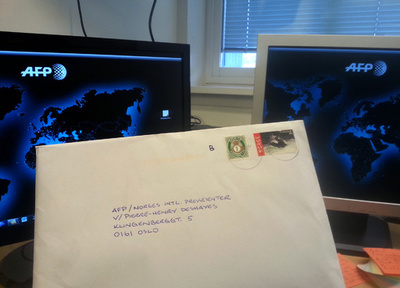【AFP記者コラム】エボラウイルスと過ごした11日間
このニュースをシェア

私たちが滞在したホテルはおいしいチキン料理を出してくれたが、熱いシャワーは言うまでもなく水道から水が出なかった。フリータウンやカイラフンには街じゅうにあった手洗い場も、ケネマにはなかった。
出発前にエボラ熱の「震源地」に行く予定だと言うと、人々は私の勇気をたたえた。だが現実はもちろん、そんな映画のヒーローのようなものではなかった。危険は冒さないことを大前提に、手は徹底的に洗い、現地住民に対しては「それ以上、近づくな」とジェスチャーで伝え、一定の距離を保った。
カイラフンとケネマで、カールとサミールは混雑する市場に入っていき、素晴らしい写真と動画を撮ってきた。でも私は「あんなところに入っていくなんてあり得ない。自殺行為だ。俺はここで待ってるよ」と、どんなリスクもとらなかった。ヒーローも形無しだ。
ホットゾーンで過ごすこと自体は、そんなに恐ろしい経験ではない。高いはしごを登ったりクモをつかんだりするほうが、勇気が必要かもしれない。だが少しずつ体が蝕まれていくような感覚に陥るのは確かだ。
何にも触れず、出会う人みんなを警戒し、数分ごとに手と顔を洗い、ちょっとした咳やかゆみに怯える生活を何日か続ければ、ストレスで押し潰されそうになる。頭からエボラ熱のことを消すことはできない。ずっと考えていなければ、手を洗わずに目をこすったりするなど軽率な行動をとって自分を危険にさらしてしまうからだ。
シエラレオネ東部で活動していた援助関係者たちは言っていた。エボラ熱を恐れないようになったら家に帰るときだ、と。こういった大きなニュースの記事に取り組むのは、間違いなくやりがいのある仕事だ。それでも東部からフリータウンに戻ってきたころには、私はもうこの国から出る準備ができていた。
エボラウイルスの潜伏期間は最長3週間だといわれる。それまで同僚との握手を断らないといけないが、ランチタイムの皿洗いやコーヒー当番を免除されるのは嬉しい限りだ。
私はサミールとカールと約束した。世界の人々がもう一つの大惨事のことを思っている9月11日に、3人とも無事に3週間を迎えることができたら、スカイプ(Skype)越しにエボラ熱の犠牲者を悼んで乾杯しようと。(c)AFP/Frankie TAGGART
この記事は、AFP通信のセネガル・ダカール在住の記者、Frankie TAGGARTが書いたコラムを翻訳したものです。(ツイッター:@frankietaggart)