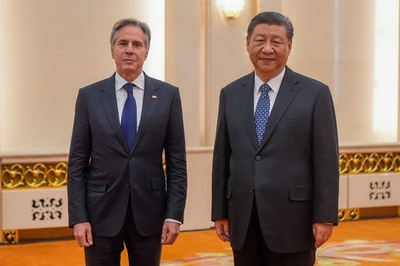津波生存者が語る、認知症介護施設を襲った悪夢
このニュースをシェア

【3月15日 AFP】オオハシカオリさん(39)が見たのは、家屋を飲み込み、田畑をなめつくしていく泥とがれきの巨大な波だった。すぐさま自分が働く高齢者施設へ向かった。
ドライバーを乗せたまま、荒れ狂う水のうねりに投げ出される車。どうにか木にしがみついた人びとも、波間に引きずり下ろされていった。日本史上最大の地震がもたらした巨大津波だった。これで終わりだと思った、と語るオオハシさん。甚大な被害を受けた宮城県の仙台沿岸にある高齢者施設で、オオハシさんは職員15人と、重い認知症を持つ入居者200人と身を寄せ合いながら、悪夢の2晩を過ごした。
■避難中も容赦なく続く余震
二重の大天災に襲われた11日、施設の1階があっという間に泥水でいっぱいになると、オオハシさんと同僚は必死でお年寄りたちを2階と3階に避難させた。
その間もずっと、大きな余震が続いた。雪が降り始め、停電で真っ暗になった。悪夢だと思った、とオオハシさんは話す。お年寄りたちのために気持ちを強く持とうとしたが、すぐに厳しい冬の寒さと孤立感に包まれた。誰も助からないと思えた。
しかし、オオハシさんたちはお年寄りたちの世話に追われた。懐中電灯の明かりの下で、ツナの缶詰やわずかなパンを少しずつお年寄りたちに食べさせた。闇の中でトイレを手伝い、固い床の上にマットを敷いた。
入居者はみな怖がっていたという。津波だと分かってはいなかったと思われるものの、部屋が暗くて寒いと言って怖がる人もいた。多くの人が何かが違うという意識はあって、夜中の2時、3時まで寝つけずにいた。完全に孤立していたものの、またいつ津波や地震が来るか分からないと思うと施設の建物から出るのも怖かった、とオオハシさんは語った。
■救助隊の看護師の言葉に安堵の涙
オオハシさんは携帯電話で12歳の息子と連絡が取れた。託児所に預けた2歳の娘はきっと無事だと信じた。津波から丸1日経ったころ、ようやく希望が見え始めた。水が引き、施設の上空に救助ヘリコプターがやって来たのだ。2人の救助隊員は、救援が向かっているから頑張ってとオオハシさんを励ました。
救助隊が施設にたどり着いたのは地震から2日後の13日だった。お年寄りたちが避難できるよう、がれきをのけて通り道ができた。健康診断を受けた後、お年寄りたちは家族の元へ送り届けられていった。奇跡的にもけが人はいなかった。救助隊の看護師が来て頑張りを褒めてくれた時、初めて気が抜けて泣いてしまいまったという。
■「絶対に会える」、息子との約束を胸に生き抜いた2日間
オオハシさんはその日中に、緊急避難所となっている仙台市内の学校の体育館で家族と再会できた。今も余震があるたびに、2歳の娘を抱きかかえずにはいられない。息子と電話でつながった時、絶対に会えると言ったものの、希望をなくしかけたこともあった。でも息子と約束したんだから、何としても生き残らなければ、と自分に言い聞かせたという。
オオハシさんの自宅はどうにか建ってはいるが、中は家具から何からすべてが散乱し、地震の強烈さを物語っていた。今、足りないのは情報だ、とオオハシさんは話す。救助活動の進み具合も、これから何が起こるのかも分からない。未来があるのかどうかも分からない。本当に恐ろしい気持ちでいっぱいだ、とオオハシさんは語った。(c)AFP/Hiroshi Hiyama
ドライバーを乗せたまま、荒れ狂う水のうねりに投げ出される車。どうにか木にしがみついた人びとも、波間に引きずり下ろされていった。日本史上最大の地震がもたらした巨大津波だった。これで終わりだと思った、と語るオオハシさん。甚大な被害を受けた宮城県の仙台沿岸にある高齢者施設で、オオハシさんは職員15人と、重い認知症を持つ入居者200人と身を寄せ合いながら、悪夢の2晩を過ごした。
■避難中も容赦なく続く余震
二重の大天災に襲われた11日、施設の1階があっという間に泥水でいっぱいになると、オオハシさんと同僚は必死でお年寄りたちを2階と3階に避難させた。
その間もずっと、大きな余震が続いた。雪が降り始め、停電で真っ暗になった。悪夢だと思った、とオオハシさんは話す。お年寄りたちのために気持ちを強く持とうとしたが、すぐに厳しい冬の寒さと孤立感に包まれた。誰も助からないと思えた。
しかし、オオハシさんたちはお年寄りたちの世話に追われた。懐中電灯の明かりの下で、ツナの缶詰やわずかなパンを少しずつお年寄りたちに食べさせた。闇の中でトイレを手伝い、固い床の上にマットを敷いた。
入居者はみな怖がっていたという。津波だと分かってはいなかったと思われるものの、部屋が暗くて寒いと言って怖がる人もいた。多くの人が何かが違うという意識はあって、夜中の2時、3時まで寝つけずにいた。完全に孤立していたものの、またいつ津波や地震が来るか分からないと思うと施設の建物から出るのも怖かった、とオオハシさんは語った。
■救助隊の看護師の言葉に安堵の涙
オオハシさんは携帯電話で12歳の息子と連絡が取れた。託児所に預けた2歳の娘はきっと無事だと信じた。津波から丸1日経ったころ、ようやく希望が見え始めた。水が引き、施設の上空に救助ヘリコプターがやって来たのだ。2人の救助隊員は、救援が向かっているから頑張ってとオオハシさんを励ました。
救助隊が施設にたどり着いたのは地震から2日後の13日だった。お年寄りたちが避難できるよう、がれきをのけて通り道ができた。健康診断を受けた後、お年寄りたちは家族の元へ送り届けられていった。奇跡的にもけが人はいなかった。救助隊の看護師が来て頑張りを褒めてくれた時、初めて気が抜けて泣いてしまいまったという。
■「絶対に会える」、息子との約束を胸に生き抜いた2日間
オオハシさんはその日中に、緊急避難所となっている仙台市内の学校の体育館で家族と再会できた。今も余震があるたびに、2歳の娘を抱きかかえずにはいられない。息子と電話でつながった時、絶対に会えると言ったものの、希望をなくしかけたこともあった。でも息子と約束したんだから、何としても生き残らなければ、と自分に言い聞かせたという。
オオハシさんの自宅はどうにか建ってはいるが、中は家具から何からすべてが散乱し、地震の強烈さを物語っていた。今、足りないのは情報だ、とオオハシさんは話す。救助活動の進み具合も、これから何が起こるのかも分からない。未来があるのかどうかも分からない。本当に恐ろしい気持ちでいっぱいだ、とオオハシさんは語った。(c)AFP/Hiroshi Hiyama